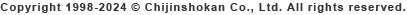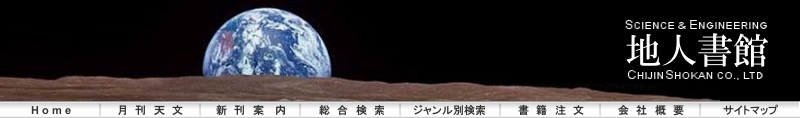

書名:天文学大事典
編者:天文学大事典編集委員会 判型:B5判 頁数:832頁 定価:25,200円(税込み) ISBN:ISBN978-4-8052-0787-1 ◆編集委員の紹介 ◆パンフレットダウンロード(PDF) ◆本文イメージ ◆本書「序文」より ◆お知らせ
本事典では『月刊天文』の「読者の天文写真」への応募作品を図版として利用させて頂いていますが、一部の作品について連絡先のわからない方がいらっしゃいました。お心当たりの方は、以下詳細をご覧ください。
>詳細 |
◆『天文学大事典』の刊行について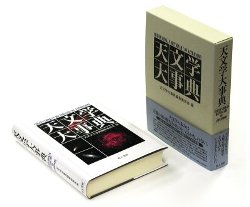 弊社では、過去に『天文観測辞典』(古畑正秋監修、1977年)、『天文学辞典』(鈴木敬信著、1986年)、『天文小辞典』(J.ミットン著、1994年)といった天文学関係の辞典を刊行してきました。それぞれに個性ある天文辞典として好評を得てきましたが、今回、21世紀にふさわしい本格的な天文学の大事典として、『天文学大事典』を刊行いたしました。日本を代表する130人の天文学者、天文教育普及関係者によって、約5000項目の天文用語が解説されています。
弊社では、過去に『天文観測辞典』(古畑正秋監修、1977年)、『天文学辞典』(鈴木敬信著、1986年)、『天文小辞典』(J.ミットン著、1994年)といった天文学関係の辞典を刊行してきました。それぞれに個性ある天文辞典として好評を得てきましたが、今回、21世紀にふさわしい本格的な天文学の大事典として、『天文学大事典』を刊行いたしました。日本を代表する130人の天文学者、天文教育普及関係者によって、約5000項目の天文用語が解説されています。日本では、しばらくの間、中規模、小規模なものをのぞいて、本格的な天文学の事典(辞典)が刊行されていません。また、書名に「事典」とはあっても、各見出し語が五十音配列で構成される通常の事典形式ではない書物もあります。翻訳書ではない、日本人の執筆者による天文学関係の事典も、約20年間出版されておりません。今回の『天文学大事典』は、その意味で待望久しいものと言えます。 ◆天文学大事典編集委員会■編集主幹山田 卓■編集幹事 池内 了 佐藤修二 澤 武文 森 暁雄 森 治郎■分野別編集委員 池内 了 内田 豊 岡村定矩 奥田治之 加藤賢一 斎尾英行 桜井 隆 佐藤修二 澤 武文 祖父江義明 西村史朗 野田 学 福島登志夫 槙野文命 山田 卓 山本哲生 吉川 真■制作編集委員 小林修二 鈴木雅夫 野田 学 本夛康郎 毛利勝廣 山田吉孝 ◆天文学大事典執筆者青木 勉 青木和光 阿部 豊 荒川政彦 荒船次郎 有本信雄 安藤裕康 家 正則 池内 了 井田 茂 市川 隆 一本 潔 伊藤孝士 井上 一 内田 豊 梅原広明 海老塚昇 榎森啓元 太田耕司 岡田達明 岡村定矩 小川英夫 奥田治之 小倉勝男 尾崎洋二 梶野敏貴 加藤賢一 加藤正二 株本訓久 川村静児 草野完也 久保良雄 久保岡俊宏 倉本 圭 黒河宏企 小笹隆司 小玉英雄 後藤真理子 小林憲正 小山勝二 斎尾英行 阪本成一 桜井 隆 佐々木節 佐々木稔 定金晃三 佐藤修二 澤 武文 芝井 広 柴崎徳明 柴田一成 柴橋博資 嶋作一大 末松芳法 鈴木雅夫 関井 隆 関口和寛 相馬 充 祖父江義明 多賀正敏 高橋忠幸 高原文郎 高原まり子 高見英樹 田近英一 立松健一 田中培生 田中 済 田原 譲 千葉柾司 辻 隆 出口修至 出村裕英 寺薗淳也 土佐 誠 長沢 工 中嶋浩一 中島 弘 中田好一 仲野 誠 永原裕子 中村昭子 中村 士 中村正人 中村泰久 永山幸男 西川 淳 西村 純 西村史朗 野口正史 野田 学 蜂巣 泉 馬場直志 濱部 勝 日江井榮二郎 平尾孝憲 平田龍幸 福江 純 福島登志夫 藤本正行 布施哲治 細川瑞彦 本間希樹 前田恵一 牧島一夫 槙野文命 松浦周二 松原英雄 松村雅文 満田和久 宮崎 聡 三好 真 村上 泉 毛利勝廣 森田耕一郎 柳澤正久 山田 卓 山田 亨 山田吉孝 山中大学 圦本尚義 横尾武夫 横尾広光 横山紘一 吉川 真 吉森正人 渡部潤一 渡辺 堯 渡邊鉄哉 度會英教 ◆『天文学大事典』刊行の主旨■21世紀の天文学21世紀に入って、ようやくわれわれはビッグバン宇宙を受け入れ、宇宙が常に変化しかつ有限であることを認識した。そして、宇宙の中での人間の位置というものを、それまで数千年にわたってわれわれのよりどころであった“神”に代わって、科学が教えてくれるのかもしれないと感じ始めている。宇宙の誕生を語る一般向け解説書がベストセラーとなったのも、世界中で巨大望遠鏡が次々と建設され、ハッブル宇宙望遠鏡や探査機による観測が成果をあげているのも決してこのことと無関係ではない。今、だれもが自分の宇宙をもっとよく見たい、そして自分と宇宙の関係をもっとよく知りたいと考えている。 当然、新聞、雑誌、テレビ等、マスメディアでこの種の内容がとりあげられる機会は多く、一般の人々がこれらの関連事項についての疑問や興味を持つケースもますます多くなっている。ところが、著しい観測機器、観測技術の進歩と、データ解析能力の飛躍的な進歩により、その成果は質、量ともに増大し、内容は次々と短期間に新しく書き換えられている。拡大する多くの分野の詳細を知ることは、一般の人々のみならず、研究者にとっても、教育関係者にとってもたいへんむずかしくなってきている。 ■天文用語 『天文学大事典』は、こういった現代の要望に応えられるものとして編集された。一般社会人が天文学の用語に接する機会は、かつては、テレビのニュースや新聞・雑誌など編集・整理されたものであったが、現在ではインターネットの検索機能などによって、専門家向けの生の術語に接する機会が格段に増えてきた。その用語の解説をネットの中から探し出すことも容易であるが、さまざまな意図で発信されている玉石混淆の情報の中から目的にあったものを探し出すのは困難を伴うのが実態である。 『天文学大事典』においては、簡潔な定義的な説明と、重要度と必要性に応じて書き加えられた解説を組み合わせることによって、読者の要求に応えられるようにした。専門用語の中には、字面からは想像できない分野で使用されている術語もたくさんある。本書の語釈や解説は、科学系のジャーナリストなどが、天文学関連の記事を書く上で、その用語の適用範囲や実際に使われる場面でのニュアンスを知るためにも役立つはずである。 また、最近はサイエンス・コミュニケーションの重要性が認識されるようになり、科学者自身が、一般読者向けに記事や解説を書かなければならない機会も増えている。その際、自分が専門とする分野の用語が、一般的にはどのような使われた方をされ、また、周辺分野の術語の定義を確認しておくことは、サイエンス・ライティングの基本となるものである。さらに、教育関係者にとっては、教科書等に記述された天文学の基本事項に、多方面からの付加情報を添えて、授業や講義をより豊かな内容とするために役立たせられる見出し語の解説を心掛けている。 ■アマチュア天文学 また、弊社は半世紀以上にわたって、天文雑誌・天文書籍を通じて、日本の天文学の普及活動にかかわりを持ち、専門家と多くの天文ファンとの間の架け橋という役割を担ってきた。天文学には、アマチュアの観測家、研究者が活躍してきた歴史がある。そして、伝統あるアマチュア天文学の世界には、天文学の公的な学術用語以外にも、独自に使用され進化してきた用語がある。これはもちろん日本に限られたことではない。弊社が刊行する天文学の事典である以上、見出し語には当然のことながら学術用語集には収録されてなアマチュア用語も収録されている。 ◆『天文学大事典』刊行の経過■企画と編集 本書が企画されたのは1997年のことである。1977年に刊行された『天文観測辞典』(古畑正秋監修、「新版」は1983年)に代わる新しい天文学の事典を企画していく中で、この『天文学大事典』の構想は生まれた。名古屋市科学館で30年にわたってプラネタリウム解説者として活躍され、天文学の普及に尽力された山田卓氏に企画を提案すると、山田氏からは天文ファンやアマチュア天文家だけを対象にした辞典ではなく、もっと広い範囲の読者に使ってもらえる事典にするとの方針が打ち出された。 山田氏の幅広い人脈によって、日本を代表する天文学者から科学ジャーナリストまで編集委員として加わっていただくことが可能となった。さらに、現代の天文学を便宜的に対象天体と観測波長などで15の分野に分け、それぞれ分野別に最適な分野別編集委員を委嘱した。これらの編集委員に加えて、山田氏の薫陶を受けた名古屋市科学館の天文学芸員の方々にも参加していただき、まず本事典で取り上げる見出し語の選択作業から編集作業はスタートした。 最初に、内外の主要な辞典、用語集から1万語以上の天文用語を収集し、重複などを整理してそれらを15分野に便宜的に配分した。次に、各分野別編集委員が、各分野の特色を生かしつつ配分された見出し語を重要度によって、解説分量として大項目、中項目、小項目に分類し、それぞれの項目を執筆する適任者を選び、地人書館より各執筆者に執筆依頼を行ない、日本の天文学の各分野で活躍する130人に承諾を得たのが1999年秋のことであった。 ■原稿回収 当初、2000年中には原稿の回収を済ませる予定であったが、執筆者それぞれの事情で執筆の遅れが生じ、2001年半ばでも回収率は7割程度であったが、分野ごとに分野別編集委員による執筆済み原稿の査読作業を開始した。その後、原稿執筆の督促と原稿回収を進めながら、並行して査読作業を進める状態が2年以上続いた。 当初の予定が大幅に遅れる中で、編集委員や130人を超える執筆者の中には、鬼籍に入られる方もおられ、新たな編集委員、執筆者の委嘱も行なわれた。最終的に、ほぼすべての原稿を回収し、編集員による査読作業が終了したのは、2005年に入ってからであった。それまでに、各分野別編集委員とは独立に、科学記者の立場から森暁雄編集委員にはそれまでに回収された原稿すべてに目を通していただいた。そこでの疑問、要望に、編集作業中に気づいた疑問点などを含め、各分野別編集委員、各執筆者へ問い合わせ、および加筆・訂正作業依頼を行ない、2005年秋にはそれらを回収した。 ■編集制作作業 編集作業が遅れている間にも、天文学の世界では新しい発見があり、本書の企画段階では計画段階であったプロジェクトが現実のものとなり、最新の観測機器の開発され運用されはじめている。これの影響を最も受けるのが、高エネルギー天文学の分野や惑星科学の分野であるが、特に、高エネルギー天文学の分野では、当該分野担当の槇野文命編集委員によって、ほとんどの項目について最新情報に基づいた加筆・訂正が行なわれた。 2005年秋からは、最終的な原稿整理作業に入るとともに、各原稿の最終チェック作業を開始し、2006年春に完了した。2006年夏からは本文原稿の組版作業を進めるとともに、図版、画像の処理が行なわれた。また、2007年からは、新たに見つかった不足項目の執筆などを並行して進め、2007年5月にはすべての校正作業を完了し、6月刊行となった。 |